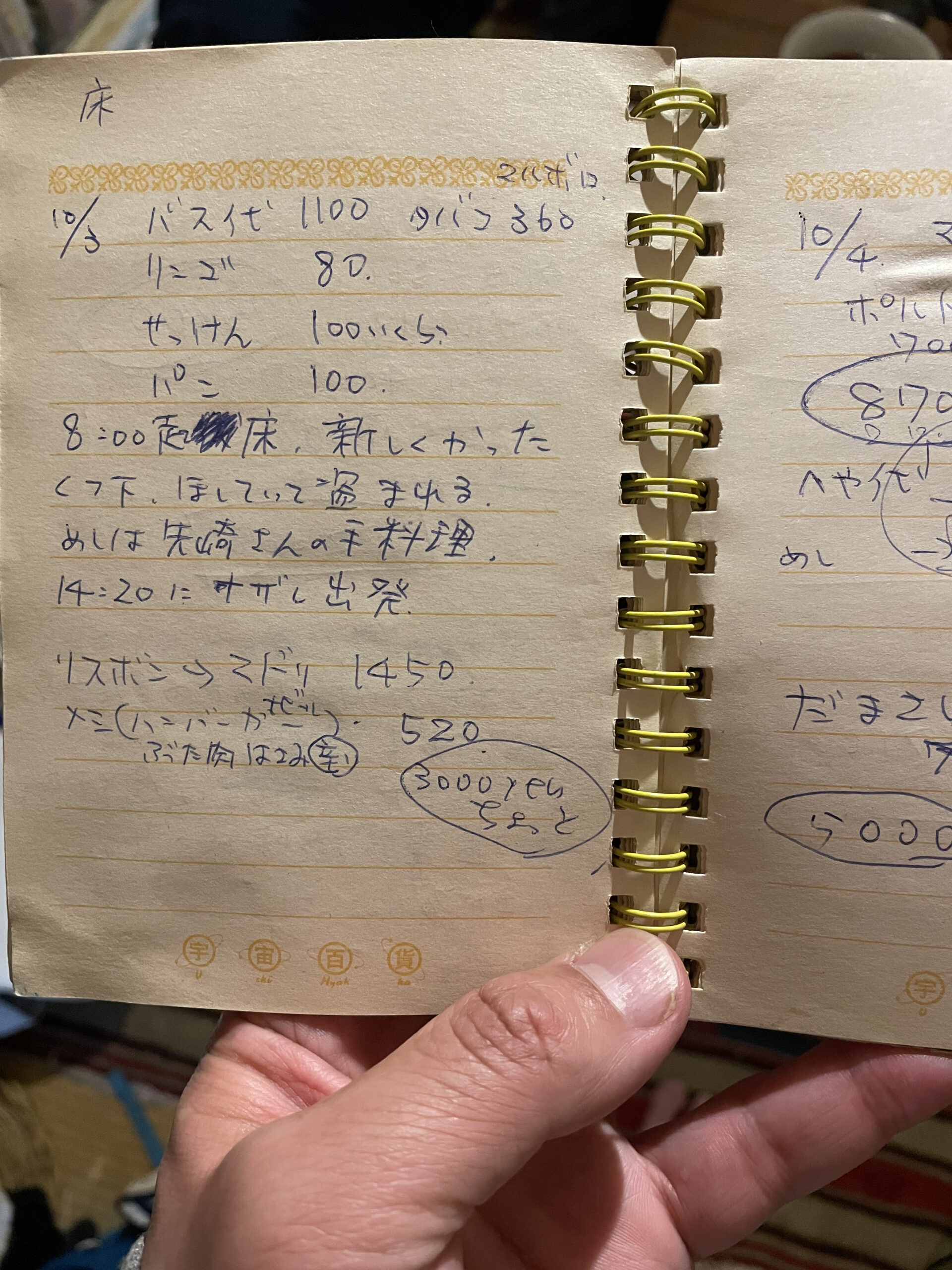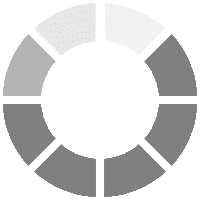いつだったか、とある場所へ出張に行った時のこと。
どこかへ出張に行った時には、出来るだけふたつの場所に行くように自分は決めている。それはレコード屋と居酒屋で、地元にある昔ながらのレコード屋と、ひとりでゆっくり飲めるような古くて落ち着いた居酒屋をあらかじめ調べて探しておく。だからどこに行っても時間を持て余すことはまず、ない。
その時もやっぱりレコード屋に居た。どこか熊本に似た香りのする、ちょうど良い大きさの海沿いの街。商談は朝からもう済んでしまったし、帰りの便は夜だし、つまりその日、時間は豊富にあった。
そのレコード屋にはオープンの11時から行ったのだが、それにしても良いレコード屋だった。古くからその地にある店らしいのだけど、何しろ品揃えがいい。店主の目利きと意思がはっきりと伝わる古いレコードのチョイス。店内もなかなか広く、在庫も多いので、これは一日中居ても飽きないなと、ひとつひとつ真剣に見ることにした。
カウンターに下を向いて座っているのが、このレコード屋の店主らしかった。歳の頃なら50半ば、こういうタイプのレコード屋にいかにも居そうな、どこか一癖ある雰囲気があって、見ようによっては作家の村上春樹に似てなくもない。下を向いてひたすら値付けだかをなにかをしている、陰鬱とも言える感じの男。ちょっと話しかけづらいムラカミさん。自分はこっそり、そう名付けることする。でも実は彼がこの話の主要な人物ではない。
時間も忘れてもうすでに5枚くらい選んだ頃だったろうか。おそらくお昼を過ぎたあたりになって、ひとりの女性が店内に入ってきた。自分がレコード探しにひたすら熱中していたからなのか、最初はまったく気がつかなかったのだが、店内の空気というか香りが少し変わったことに、ふと気づいたのだ。でもそれは香水、というようなあからさまな香りではなかった。
見たところは30半ば、紺と呼ぶには少し淡いブルーのスウェーターに白のパンツ、ベージュの軽いコート、靴はアディダスのスタンスミスだったか。いずれも洋服の仕立て、見るからに生地が良く、普段からまず女性の服装を覚えることのできない自分が、こうして後から羅列できるくらいだから、たぶんそれはどこか印象に残る着こなしだったのだと思う。
その姿をひとことで美しい、と言い切ってしまってもいい。でもいま思い出せば、それはただ美しいというより、どこか小動物のようなかわいらしさを含んでいたとも言えるし、結局それは「品のあるひと」という言い方がいちばん落ち着くような気がした。レコードを見るフリをしながら、決してじろじろと観察していたわけではないが、何しろ店内には僕と彼女(そして店主であるムラカミさん)しかいないので、まぁ自然にそうなってしまう。
「・・・あのー。すみません」
彼女がこの僕に話しかけているのだと気づくのに、ずいぶんと時間がかかった。いや、実際は一瞬のことだったのかもしれない。でもとにかく驚いて店内が瞬間的に止まったのは確かだった。
「わたし、レコードを探しているんですけど」
彼女は確かに、僕に向けてそう言っている。・・・あ、いや、あのう、僕はここの店員ではなくて・・・すぐさま、そう答えようとしたのだが、あろうことか、自分は反射的にこう言ってしまう。
「・・・え、なんのですか?」
なぜそう答えてしまったのだろう。今でもそれが自分でもよくわからない。すでに馴染んだ店の雰囲気がそうさせたのか、あるいは恥を晒せる知らない土地だったからか、それともやはり彼女が品良く美しかったからか。今となってみれば、理由はそのすべてだったような気がしているが。
「探しているのは具体的に誰々のレコード、というわけじゃないんです。少し説明すると・・・」
立ち話で聞いてみると、最近彼女は知り合いからレコードプレーヤーをもらって手に入れたらしく、何かレコードが欲しいのだけど、でも元から自分はそこまで音楽に詳しくない。できればそのレコードはインテリアとして部屋に飾っても良くて、そしてもちろん内容が良いものが欲しいのだけど・・・ということらしかった。
「そのレコード、ジャンルはなんでもいいんですか?」と、なんとなく聞いてみる。
「ええ、それは別に。・・・でも。まぁ、なんていうんでしたっけ。・・・メタル? なんかは少し困るかもしれないけど」
彼女がゆっくりといたずらに微笑みながらそう言った時、僕のなかで何かが弾けたのだけど、でももちろんそんなことは表に出さず、すたすたと別のコーナーに歩いていって、とあるレコードを手に取って彼女に差し出した。そのレコードはさっき見つけていたのだけど、もうすでに持っているので買わなかったもののひとつだった。
「そういう話だったら、僕ならこれを選ぶと思います。ポール・デスモンドという人の『BOSSA ANTIGUA』というレコードですけど」
「ふうん。これは・・・ジャズ、になるんですか?」
「うーん。まぁジャンルでいうとそうなるんだろうけど、でもどうだろう・・・。なんとなく誰かが気分良く歌うハミングみたいに聴こえる時もあれば、例えば洒落たどこかのホテルのラウンジなんかでかかってる音楽にも聴こえたり。そもそもジャズの人がブラジルのボサノヴァをやっているレコードですが、リーダーのポール・デスモンドはアルトサックス、一緒にやっているのがジム・ホールというギタリストで。とにかくふたりとも、素晴らしく品のいい演奏をするんです」
そう、それはまるであなたがいま着ている服みたいに。なんて馬鹿みたいにキザな言葉はもちろんここでは閉まっておく。
「このジャケット、なんだかあたたかい感じでいいですね」
「うん、内容もまさにこのジャケットみたいな感じなんです。レコードを聴きながらジャケットを眺めているだけで、その空間が親密で豊かになるような。そこが何より素晴らしくて」
「良かった。これにします。選んでくれてありがとう。・・・ところで、もしかして、他の県から来た方なんですか? なんだか話す言葉とか雰囲気が」
「ええ、そうなんです。実は、ここには仕事で来ていて」
・・・さて。そのあとのことはもちろんここには書かない。
ただ、ふたつだけ分かったこと。ひとつは、やはり品のある彼女のインテリアにそのレコードが素晴らしく似合っていたということ。そしてもうひとつ、彼女は最初から僕を店員と間違ってはいなかったということ。「そんなわけないじゃない」。彼女はあのいたずらな微笑みで確かにそう言った。
・
これはずいぶん前にみた夢の話。いや、たしか、そうだと思う。