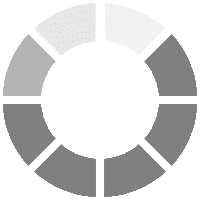昔から、8月もそろそろ終わりに近づくと、誰から頼まれたわけでもないのに、なぜか勝手に読書感想文を記したくなります。やっぱりそれは自分にとって今は亡き、夏休みの名残というものでしょうけども。
それでも最近はそもそも本というものをまったく読まなくなってしまいました。なんと言っても子育てを含めたあらゆる日常が忙しく・・・というのは完全なる言い訳で、本当に好きな人はどんなに短い一瞬でも見つけて自ら進んで活字を追うでしょうし、気がつけば本そのものをそぞろ手に取って手触り自体を味わうでしょうから、結局のところ、自分は本当の本好きではなかったということだろうな、と今たびたび想っているところです。
そういう自分が久々に「これはいいな」と思いながら最後まで読み進めてしまったのが、この田口史人という人が書いた『あんころごはん』(リクロ舎)という本です。
うちの店の下のイベントスペースでもあるtsukimiさんで「mychairbooks」さんが出店されていた時、たまたま見つけて買った本ですが、これは買う前からその文庫本自体から妙に素敵なオーラがはっきりと見えました。正直言って、別に装丁なんかも特に凝っているとは思えないのだけど、それははっきりと見えたので、やっぱりなにか漂うものがあったのだと思います。ちなみにその時、うちの奥さんも後から来たのですが、彼女も同じようにこの本を手に取って買おうとしていたので、それが見えたのは僕だけでは無いようです(でも写真の通り、この雨にやられちまって、すでにヨレヨレになってますが)。
そもそもそういうエピソード自体、この本に即して言えば、「思わず、なんとなく入りたくなる街の定食屋さん」を見つけた時の感触にひたすら近いかもしれません。これはつまり、著者が生きていくうえで出会った、数々の忘れられない飲食店の思い出の集積であり、その中には素晴らしく美味しい店もあれば、まったくそうでは無い店、そして最も重要なのはそのどちらでも無い、なんとなく美味しくもあり特別美味しくも無い店、というものがいかに自分にとって、そして多くの人にとって大切か、ということを問うた本とも言えると思います。
うん、そりゃ確かに僕らは飲食店にはまずもって美味しいものを求めがちですが、でも生きていくことに必要なのは、決して食べて美味しいものばかりではありません。そこで働くひとたちの表情やその想いのようなもの、そこに流れるヴァイブスや雰囲気、そのすべてを感じては浴びながら、僕らはそのすべてを通して味わっていると言えるわけで、例え味は普通であっても、いや逆に普通だからこそ、深く長く味わえるものだってあるわけです。そして確かに、そういう普遍的な愛おしさを持った店というのは、今の時代、総じて少なくなって来ている気がします。
なぜといえば、きっとそういう店こそ、圧倒的に個人でなければ生み出せないから。企業的リサーチや統計なんかでは、到底そこに到ることはできないだろうから。それこそ、この本にあるような、長年通っている店を切り盛りしているおじちゃんやおばちゃんがだんだん歳を取ってきて、徐々にその盛り付けが荒くなってきたり、味付けのポイントが少しずつゆるんできたりするような、いかにも香ばしくて人間らしい風景というのは、数値だけの世界では許されたり生み出せたりするわけがないからです。そんないわば体温のある風景こそ、胃袋のみでなく、僕らそのものを満たしてくれるのだろうと。
そういえば、この本を読んでいて、僕もひとつ、とあるお店の記憶が蘇ってきました。
それは学生だった頃。当時一人暮らしをしていたアパートの近くに、不思議なお弁当屋さんがあったのです。どう不思議かと言えば、そのお弁当のすべてが完全に洋風だったからです。
元々フレンチだかのシェフだった人が開いた、洋風のお弁当屋さん。だからなのか、いわゆるど定番の唐揚げやトンカツもなく、主にホワイトソースやデミグラスソースがかったものだとか、そんな感じのメニューのみ。なにせコンセプトが見えにくいというか、ちょっと不思議な店。近所も近所だということもあったけれど、それでも結構通ったので、味は悪くはなかったように思います。
ただ、やはりなかなか他にない奇抜ともいえる店を出すくらいなので、やっているその人はどこか野方図でアナーキーな匂いがする人でした。僕としては味そのものよりも、その人の記憶の方が強いのです。
年の頃なら40後半で色白く、髪が少しM字気味にそりあがっていて、ちょっと口調はべらんめぇな勢いというか、どこか乱暴な感じではあった。多分想像するに、幾度の度重なるハードな料理修行を潜り抜けてきた上での血走り気味な勢いというか、きっとこの弁当屋もそんな修行をようやく終えた上での大いなる勇み足の第一歩目、ということが容易に想像できる感じ。
いやいや、もしかしたらそれは完全に新しいチャレンジというか、敢えて誰もやったことのないことへの挑戦だったのかもしれないけれど(だってこのテイクアウト全盛な2021に振り返るとあまりに早すぎる試みだった気がするから)、とにかく、こちらが勝手に受けた印象でいうと、至る所にやけっぱちなスタートの匂いは確かにした。その店だって客がすれ違えないくらいに狭かったし、メニューだって定番というものが一切無く、その日行ってみなきゃわからない、常にぶっつけ的なものに思えたし、でもまぁもちろん僕は逆にそういうのが好きなので敢えて通っていたのだけども。
そして、やはり、というべきか、そう長くはないとある日、その店はなくなってしまいました。あのシェフは今ごろどうしているのだろう。
それにしても妙な感じだったのは、鳥もも肉のバルサミコ風ソテーだとか、帆立たっぷりのクリームシチューかすかにレモン風味だとか、そういう少し高貴なものを、しがない一人暮らしの大学生がカビ臭いアパートでもそもそと食べることで、それはやはりどこぞの唐揚げ弁当を食べるのとは違っていたということです。でもだからこそ、その弁当屋の記憶と当時の日々はありありと覚えています。
いずれにしても、結局、自分の中でそういう記憶に残るような店をひとつでも持っている人は幸せというべきだし、もしあるのなら今のうち、じんわり味わって置いた方がいいように思えるのです。そんなことを思い起こさせてくれるだけでも、この本はとても貴重だと思います。