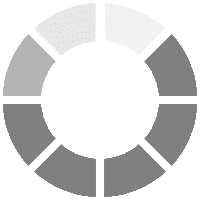『ライフ・イズ・ジャーニー』。そんなおよそラーメン屋の店名とは思えない店のこと知ったのは、果たしていつだっただろう。もう覚えていないが、多分、SNSでどこかから流れてきたとか、はじまりはそんな些細な感じだった気がする。
そして初めて食べに行った時のことも、もう覚えていない。ひとりで行ったのか、誰かと行ったのか、それはお昼なのか、夜なのか。でも最初に行った時から店内ではシブいブルースがかかっていて、壁にはギターがかけてあったので、「どうやらそういう音楽が好きな店主らしい」と感じたのではなかったろうか。
店主の斎藤くんと最初に話したのはいつだったろう。ラーメン店『琥珀』の橋本くんがまだ『カフェ ヴィアーレ』をやっていた時、何かのイベントで彼のラーメンを出してもらったことがあるのだけれど、あの時期くらいから少しずつ仲良くなっていった気がする。
しかし店主の斎藤くんといえば、とにかく不思議なひとだ。飲食店の店主というのは、どこかしら不思議なひとが多いというのが僕の勝手な持論なのだが、その中でも彼は一際変わっている。いや、変わっているというか、とにかくバランスが不思議なひとなのだ。
まず、その見かけが怖い。いかつい。実際元ボクサーなので、そのいかつさは保証書付きなのだが、『はじめの一歩』的拳闘ファイターなオーラが肩甲骨あたりからメラメラと迸っている。でもそうかと思えば、笑うと(案外よく笑うひとだ)その怖顔がコアラみたいにパッと変わって、その落差に見事やられてしまう。確か本物のコアラも実際喧嘩が強いらしいから、あながちその関係は遠くはないかもしれない。
種子島出身でいかにも酒が強そうだが、実はあまり酒は呑まない。少なくとも僕は彼が呑んでいるのを見たことがない。反対に彼は僕が呑んだくれているのを、まるでかわいそうなひとを見るように、よく厨房から眺めていたものだ。というのも、僕はジャーニーに通うようになってからは、シメのラーメンどころか、最初から呑みに行くことが多かったから。最初からシメまでラーメン屋のジャーニーで、という黄金パターン。なぜと言えば、ジャーニーにはビールはもちろん、種子島産の『南泉』という焼酎があって、他ではほぼ出回っていないという、それは種子島出身の彼だからこそ扱える秘酒だったのだ。
彼は呑んだくれの僕にいつだってその酒をきっぷよく出してくれた。彼と同じくらいにキラーでハードパンチャーなその焼酎の破壊力たるやまさに恐ろしく、あけすけにネイティヴでしかしまっさらな味で、大好きだけど末恐ろしい酒だった。だから最後はいつも決まってドロッドロに酩酊した。シメのラーメン? 実は食べたその記憶さえ、ほとんど残っていない(毎回必ず食べたらしいけど)。
うちの店でジャーニーの何周年かを祝うイベントを企画した時のこと。その日は天草大王でスープをとった限定の塩ラーメンやオリジナルのグッズやジンを売ることにした。ジンのために僕が彼にインタビューして記事を作ったり、グッズのデザインはこれまたジャーニー・ヘッズのカテジナのきんちゃんにお願いしたりした。でもそれだけではなくて、僕が何よりそのイベントでしたかったのは、どうしても彼自身を店のカウンターから引っ張り出すことだった。僕は彼という人間の面白さを十二分に分かっていたので、彼という人をもっと多くの人に知ってもらいたかった。何よりこんな人だからこそ、こんなラーメンを作ることができるんですよ、ということをどうにか誰かに知らせたかった。
だからこそ、彼にラーメンに関するトークをお願いしたのだが、彼はその直前の直前まで「いやです、絶対何も話しません」と僕にうそぶいた。どんなにお願いしても、冷たくしつこく、うそぶき続けた。実際なかなか難しくて読めないひとでもあるので、本当に話さない可能性は大有りだったし、でももうお客さんを呼んでいたので、主催側としてはギリギリまで胃が痛かった。今でもあれは思い出したくない想い出のひとつだ。
でも蓋を開けてみれば、もちろんトークはうまくいった。まったく彼は頭の回転が速いひとで、こちらが聞きたいことを投げると、すぐに察して素晴らしい答えを打ち返してくれた。話を聞けば聞くほど、強い信念を持ったひとなんだな、とその時に感じたものだ。でもそういう時に、最後までこちらにうそぶき続けるのが彼の独特のバランスというか、愛情の裏返しのようなものなのだなと、終わってからやっと気づいた。やっぱり不思議なバランスのひとなのだと思う。
「いつでも、誰にだって、包み隠さず、ラーメンの作り方を教えます」。それが彼の口癖というか、根本精神だった。僕が惚れてしまったのは、彼が作るラーメンの味だけではなくて、その考え方だった、と断言してもいい。あくまで企業秘密なる、世知辛きこの世界。そんな中で、小さな自分だけの目先の利益よりも、ひとりでも作り手が増えてそのシーン自体が大きくフックアップされていく方が、最後にはこちらにだって利益が返ってくるはず、ということを彼は腹から分かっていた。言ってみれば彼が作るラーメンというのは、そんなすべてを引き受けた味だったのだ。
「もう毎日毎日、豚の顔を見ながらスープをとりたくない」。気がつけば彼がそんなことを僕に溢すようになったのはいつ頃だったろうか。彼はなにより時代の雰囲気のようなものを敏感に感じるひとだから、ベジタリアンやヴィーガン、二酸化炭素の排出や気候変動の問題とか、そんないろんな面から言っても豚骨スープという存在そのものが、そろそろこの時代にそぐわなくなって来ているのかもしれない・・・ということを、いち速く肌で実感していたのだと思う。少なくとも毎日毎日豚の顔と睨めっこしつつスープをとりながら、いろんなことを考えていたはずだ。「そうだよなぁ、なんだか焼肉屋なんてのも。ねぇ?」。鹿児島の黒豚でとった、あくまでしつこさ皆無のクリーン極まる豚骨スープ、多くの女性をも魅了したあの素晴らしいスープを啜りながら、まるで引き裂かれるような想いで、僕もそんな風に答えた気がする。
おそらくジャーニーの暖簾があの狭い路地に上がる事はもうないだろう。少なくともあの場所においては。考えてみれば物事の終わりというのは、本当にあっけなくて素っ気無い。店なんてものは無くなってしまったら、もう終わりなのだ。何より斎藤くんが作らなければ、あのラーメンはこの世に一滴も存在せず、誰も啜ることさえできない。いたってシンプル極まりない話だ。でもだからこそ、その尊さにこそ、僕らは途方に暮れてしまう。
彼はもう旅することを止めてしまったのだろうか。
いやいや違う。また違う旅が始まったのだ。農という道を、旅を、彼はたったいま選んだのだと聞く。「・・・ラーメン、いつかまた作ります」。彼から来た僕への便りには、しっかりとそう記されている。
そう。きっと、はじまりは、ここから、なのです。
※写真:Etokikaku