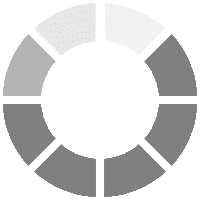先日、子どもたちを連れて南阿蘇の『久永屋』にかき氷を食べに行ってきた。
南阿蘇鉄道の長陽駅にある駅舎カフェ『久永屋』。今のいまさら、ここでわざわざその店の詳しい紹介から始めようとは思わない。地元の人間と、観光客が見事に溶け合う、まさに稀有なその空間。何よりもそれを生み出しているのが、最近はウクレレを片手に、見事豊かに「うたのお兄さん」化している、駅長こと、久永操という愉快な男。だからどちらかというとこの文章は、そのカフェの紹介というよりか、その人と自分の出会いに近いものを語ることになるはずだ。
初めて駅長である操さんと出会ったのは、とある取材だった。僕がまだ編集社にいた頃、阿蘇の地方紙の取材で彼をインタビューしたのがきっかけだったと思う。東京からこっちに帰って来てからというもの、僕は南阿蘇という場所に取り憑かれたように通っていたから、もちろん久永屋という店自体は知っていたのだけど、その場をつくって動かしている人間と、直にちゃんと話したのはそれが初めてのことだった。
いわく、実は彼自身根っからの地元の人間ではなく、九州のとある場所から移り住んだ人間であるということ。さらにそもそも独立することをすでに見据えながら、南阿蘇の様々な場所でアルバイトをしていたこと。そしてかつてアメリカのオレゴンに留学経験があったことから、そのバックボーンには何より古いモノを大切にして、それを生かしながら生活するアメリカンカルチャーが染み付いていること、などなど。ああ、なるほどなるほど。だからこそ、この現在の久永屋なのか、と頷き繋がる話ばかりだった。
いや、しかし。それにしても眩しかった。少なくとも、あの時の僕にとってはそれらすべてが眩しすぎた。
外から阿蘇の地に来て、その風景にかつてのオレゴンを感じながら、その地で働いては職人としての腕を磨いていく(久永屋は本来シフォンケーキの店だ)。そうして無人駅である長陽駅に出会い、出来るだけその古き良き場所と匂いを残しながら、その空間丸ごと、駅舎カフェとしてオープンする。その力強い足取りと圧倒的実現力。何よりも人を惹きつけて離さない、全方位に開かれたあのスマイリー・スマイル。きっとそれこそがすべてなのだろうな。ということは想像に難くない。もちろんそれまでの道のりが、こうして周りの人間が書くほどに簡単な話ではない、とわかってはいるのだけど、それでもあの当時の自分はまさに打ち拉がれるばかりだった。
というのも、その頃の自分といえば30代の後半、僕自身、独立を考えない日など無かったからだ。まさにその時の会社に骨身を埋めるつもりで東京から熊本に帰ってきたはいいものの、自分の本当の力やパフォーマンスなんて半分も出せていない気がして、日々悶々としていた。自分自身のアクの強さは自分がいちばん自認していたから、独り立ちしたほうがいいのだろうとはどこかで感じてはいたが、その術も道もどこにも見当たらないのが、その時のまっさらな現状だった。
そんな自分にとって、年下の彼から聞く話は、完全に美しいサクセスストーリーに映ってしまったし、そういう意味で、その当時の自分にとって、駅長の話はあまりに眩しすぎたのだった。
そんな僕を見据えてか、彼は取材終わり、誰にいうでもなく、なぜかこんな言葉をポツリと残した。
「・・・やっぱり、男はいつか独立したほうがいい。そして、どうせするんだったら、早い方がいい」。
そしてまさにその数年後、僕は編集社を辞めて、なんだかんだあって、現在の店を開くことになる。彼のあの時の言葉が辞めるのを早めたとは決して思わないけれど、でも常にどこかしら自分のなかで響いていたことだけは確かだ。つまり、今振り返って見ればあの取材は自分にとって、大切な句読点だったということだろう。
だからこそ、僕はこっそり彼に感謝している。そしてあの駅舎カフェに行く度に、そのことをぼんやり思い出す。結局のところ、僕にとって久永屋とは、そういう店だ。
それにしても。いつもあの場所に行くと想うのだけど、どうしてあそこでバイトをしている地元の若い子たちは、あんなにも澄んだ接客ができるのだろうか。きっとマニュアルなしの、まっさらな、ひとりひとりの若き人間としての切実な応対のようなもの。しかもみんなすべからく若いからか、心が澄んでいて、どこにも屈託が見つからない。決まって自分の子どもたちをあの場所へ一緒に連れて行きたいと思うのも、実はそんな理由があったりするのだろう。
やはりそれさえも、駅長の人徳たるものなのだろうか。いつか酒でも呑みながら、駅長自身にそのことを聞いてみなければ、と思っている。