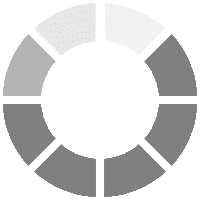思い出してみれば、子どもが生まれてからすぐ。
その頃の自分といえば、例えば『西松屋』へ行くことさえ、なんだか億劫で嫌だった。そんな場所へ行く自分というものが、どうもまだ想像できなくて、父としての準備もできていなかったのだろう。その当時、とある女ともだちから「パパ、これから頑張って!」と冗談で言われて、正直ムカっとした。あのムカっ、はいったいなんだったんだろうか、と今でもたまに考える。
でもそんな自分が何処か遠くへ消えてしまうのも、もうすぐで、オムツを替えたりミルクをあげたりお風呂に入れたりベビーカーを押したりすることにも、すぐに慣れた。そして慣れてしまってからは今度は一転して、なんで自分におっぱいというものがないんだろうか、どうして自分からはお乳が出ないんだろうか、ほんの少しくらい出ても良さそうなのに、などと案外真面目に考えたりした。
子どもを自分なりに一生懸命細かく世話をしていると、もはや父と母の違いなんておっぱいだけじゃんか、とか偉そうに思ったりしたからだったけど、もちろんそんなわけは絶対に断じてなくて、誰にとっても母は母。マザー、マンマ、オモニはそれだけでもって偉大も偉大。あのジョン・レノンだって、マザーと詩えども、決してファーザーとは詠わなかったのだから。
それからというもの、そのこと自体をなかばハウスハズバンドをしながら自分でもありありと痛感していった。うちが二人とも男の子だからだろうか、子どもが夜中に泣くのだって、ママー!と叫べども決してパパー!と叫びはしないし、寝ていながら彼らの手が本能的にまさぐり求めているのは確かに母の温もりであり、どうやら父の温かみではないようだ。だとすれば、なんだか父って必要不可欠でも無い妙な存在だよな、と思ったことを覚えている(その想いは今でも少しここにある)。
そうして、昔から感じていた素朴な疑問。どうして妊娠中のお腹の大きな女性たちというのは、誰に顔に関係なく、あんなにもすべからくおおらかで柔らかくて眩く美しいのか、ということの正解がその辺にあるような気がした。男性には到底持ち得ない、生き物としての根源的な美しさのようなもの。聖母マリア、なんて言葉が浮かんでは消えそうな。
・・・なんてことをつらつら書いていると、ついぞどこかからイクメンライターの仕事が舞って来そうだから止めておくけども(来ないって)、なんでそんなことをぼんやり思ったかといえば、下の子がいよいよ5歳を過ぎてしまって、ぷよぷよぷくぷくに柔らかく、子ども独特の良い匂いのするこの貴重な幼児期がそろそろ終わりに近づいているからに違いない。ああ、無作為に無条件に誰もが愛らしい、儚き一瞬の此の時よ。気がついてみれば、なんと、ほんのりうっすらすね毛なんぞも見えて来てしまい、親としては少しだけ・・・いやいや、かなり切ない。
保育園とか学校というのはよくしたもので、子どもが一番上の段階に近づいてくると、途端、彼らは存在的に弾かれるようにその場自体と釣り合いが取れなくなってくる。つまり、保育園において年長さんはその足音から身体つきまでもう小学生そのものであり、小学校において六年生というのはその声から自意識の隅々に至るまでもはや限りなく中学生に近い。放っておいても時間は誰からもきちんと平等に元を取って過ぎていき、その場から自然と巣立っていく。
そしてあたりまえに時はもう戻ってこない。彼らの成長とともに、家族そのものも育っていって、もちろん僕ら親も老いていく。家族とは、実はそういう一度しか経験できない過ぎ去る喪失のようなものを皆で丸ごと体現していくことなのだろうか。と、自分はたったいま、家族と生きながら実感しているところだ。
いやもちろん、その前に親として誰もが体験しなければならないらしい、あの恐ろ忌まわしき“大人はわかってくれない”反抗期、魔の中学生期を通らなければいけないらしいが。
・・・ああ、今から想像するだけで恐ろしいよ。ブルブルブルっ。
(photo.Eto kikaku)