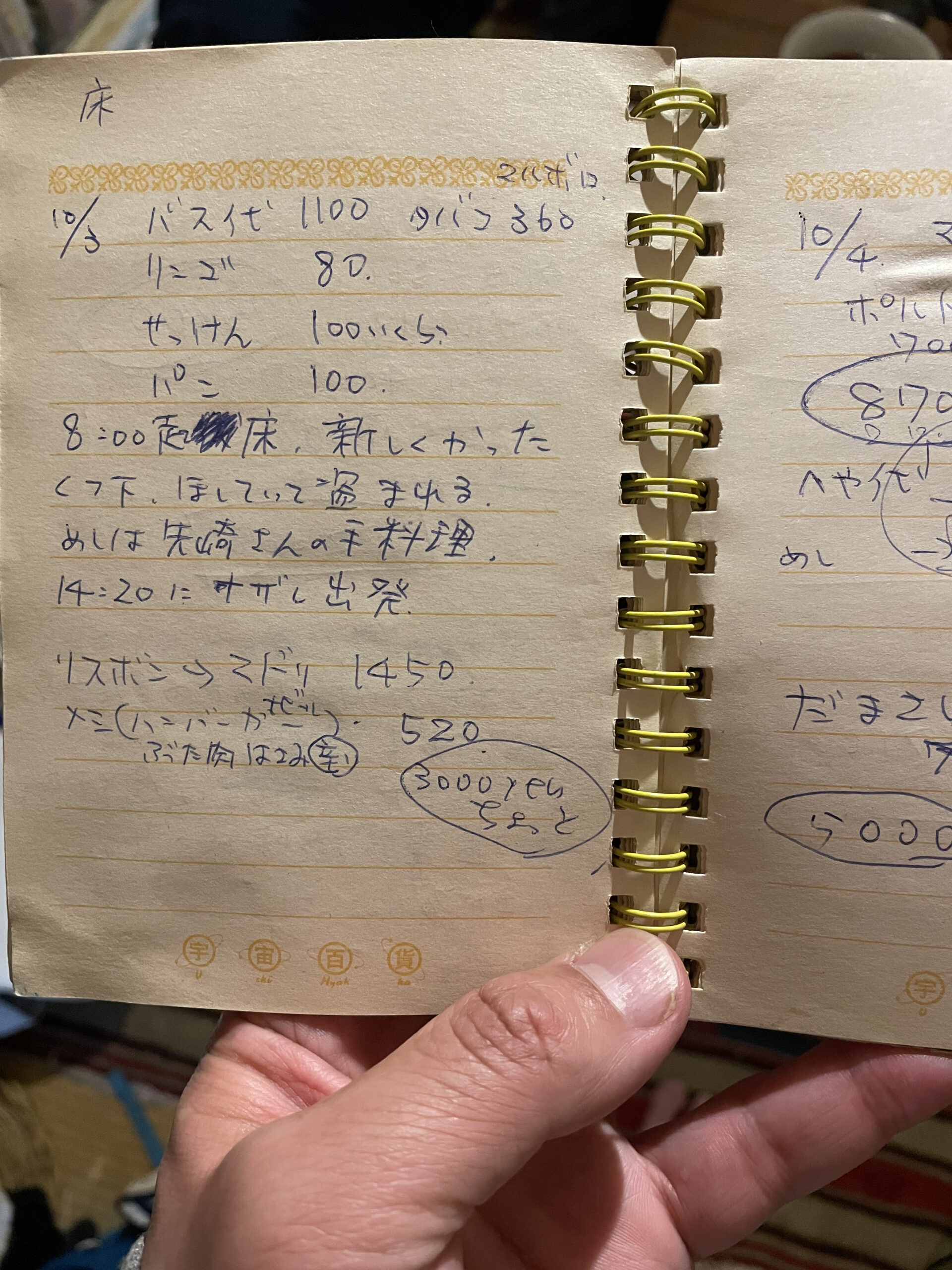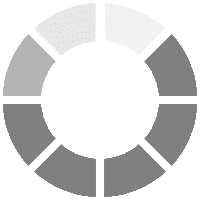大学生になったばかりの頃、とあるレンタルビデオ屋でアルバイトをしていたことがある。
そう、レンタルビデオ屋。
世にはかつて、そういうものがあったのですよ、そこゆく若者たち。文字通り、VHSのビデオをレンタルする店なんだけども。
僕が働いていたのは地元に昔からある小さなマニアックなビデオ屋だった。しかもそのマニアックさの方向が明らかにエロにエロ。なんなら品揃えの三分の二は完全にアダルトビデオで占められていて、なにしろ近所に大手のレンタル店があったのだが、そんな陽のあたる場所へは行く由も勇気もない、健気で弱気で湿り切った意気地ナッシングな漢たちがこっそりもっこり通うような店だった。僕もその陰鬱な日陰さが気にいっていたようだから、結局のところ、この僕も当時から意気地ナッシングなこっそりもっこりガイだったと言うことだろう。たぶん。
そこの店長はといえば、明らかに、いや高らかに、元ヤンキーの茶髪50代の女性。目が鋭くて痩せていて、酒が強くて、とても威勢の良いひとだった。見るからにいくつもの武勇伝持ち。
ある日、バイトに行くと、なんといきなり店長の左手に包帯がぐるぐる巻きにしてあるではないか。こりゃ明らかにただごとじゃない雰囲気、彼女の武勇伝が増えそうな匂いプンプンだ。
「・・・ゲッ!! て、店長、いったいどうしたんですか?」
話を聞いてみると、どうやらこういうことらしい。
時は深夜の閉店間際。たまたまその日は店長ひとりだけの店番だった。そんな日に限って、普段からたまに来る、明らかに目の怪しい客が来た。まぁこっそりもっこりで日陰な店だけにそんな客は多かったのだけど、とにかくその時、店内の客は彼ひとりだけ。だからして店内はおのずと店長と彼だけのBack to Backなクロージングフロアに移り変わっていく。彼の手にはむろん、熟考に熟考を重ね選び抜いたであろう、熟れ熟れのキラーアダルトな美熟女モノを三、四本ほどしっかりピック。それらを強く熱く握り締めてはレジに突き進む。そしてカウンターで店長がいつも通りそれらのビデオを「・・・ピー」とレジに読み込ませていると・・・こやつ、いきなり彼女に襲いかかって来たというのだ。
うおおっ! あ、危うし、テンチョー!!
・・・んがっ、ここで店長の“メイウェザーの秘蔵っ子”ガーボンダ・デービスばりの左クロスカウンターが炸裂する。これぞまさにカウンター越しのカウンター。ぐわしっっ! カンカンカーン!! 見事な K.O.。勝者、テンチョーなりー!!! その後、警察を呼んで事なきを得たという話であった。
今しがたこうやって書けば、この話自体、実はマジで恐ろしくヤバくて笑えない話なのだが、そして自分自身どこかしら話を盛っている気がしないでもないが、それでも店長の左クロスが恐ろしいことだけは嘘では無く、まったくもって事実である。
それはそうと、最初に書いたようにこの店の三分の二はアダルトもので、長年店長をやっている彼女はもはや仕入れるビデオを選ぶのが面倒になっていた。というか、一体全体、日陰なるこっそりもっこりな漢たちにどんな内容のブツが好まれるか、果たしてもうわからなくなってしまっているという。
という事で、仕入れるビデオのチョイス担当は僕と後輩のTの役目だった。もちろんその当時はインターネットなんてないから、サンプル映像なんてものもなくて、月々に送られてくる分厚いカタログに載っている、それぞれのアダルト女優の写真をじっくりゆっくりふたりで何回も熟読しては一本一本真剣に悩んでは選び抜いていた。
「・・・おっ! しんさん、この子、どうっスか? 『思いっきりよせてはさんでもんでぶるるんなまみまみGカップまみこ』。つーか、なんせこのタイトルのたたみ掛け具合、やばくないスか? 」
「んー、いやね、たけし。まみこも悪くなんだけどサ。オレに言わせれば、ちょっとこう・・・腰あたりのカーヴのエロみと弛みがたりんっちゅうかね。・・・んじゃこの子はどうよ?『一度だけのはっちゃけ夏、だけど二度目のぶっちゃけ大放水 ゆうこと聞かない調教フルボディ 新庄ゆうこ(仮名)」
「えー! その趣味、自分マジ、わかんないっス! ウスっ!!」
とかなんとかやりながら、選んでいたというわけです。正直、その経験がその後のどこのナニに生かされたのか、なんの役に立ったかなんてまるでわからないし、たぶんそんなものどこにもないのだろうけど、でもただひとつだけ分かったのは、結局自分にとって大事なのは「声」なのだな、という事かもしれない。
つまり、見かけがどんなに美しく可愛くても、その子の声を聞いてピンと来ないと、どうもいまいちで、なんだかグッと来ないことが分かったんです。普通に話す声にしても、なんの声にしても、とにかく声が大事。声というのは実に大切な情報というか、いわばひとつの生命線でもあるのだという事。そのことが身に染みて分かった気がする(どんな身の染み方だ)。
例えばそれは音楽でもおんなじで、いくら鳴っている音楽が良くてもその声が気に入らないと本当の意味で自分は好きになれないし、自らの内に入ってこない。ラップでもなんでもそう。
そういえば、我が生涯の一本とも言える『パリ、テキサス』という映画のテーマも「声」といえそうな気がする。それはそれはもう奇跡的に圧倒的に美しいナスターシャ・キンスキーが劇中で愛したトラヴィスことハリー・ディーン・スタントンと、お互い隔たれた部屋に居ながら受話器で話すあのシーン。あれくらい「声」の名シーンはそうそうはない。サウンドトラックにもそのシーンが入っているから、ぜひその麗しい声を聴いてみて欲しい。
2022年の今となってはもちろん、もうそのレンタルビデオ屋はない。だから実家あたりでたまに古いVHSのテープなんぞを見つけてしまうと、今でもふと、あの頃のことを思い出してしまう。もちろん、店長の左クロスカウンターの恐るべき破壊力のことも。嗚呼、店長。今ごろどこかでお元気でしょうか。
・・・とここまで書いてしまってから、以前この映画についてここで書いていたことを思い出した。いったい自分はどんだけこの映画のことが好きなのだろうか。